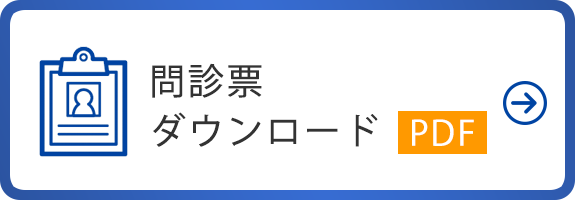診療案内
インフルエンザ予防投与
インフルエンザ予防投与の診察を行っております。詳しくはお問合せ下さい。
内科・呼吸器内科・循環器内科

- 日常よく遭遇する症状である発熱・頭痛・咳・鼻水・のどの痛み・腹痛・嘔気嘔吐・下痢・腰痛・胸痛・動悸・浮腫・めまい・倦怠感などがみられ気になる場合は、ご相談ください。
- 高血圧症、脂質異常症(高脂血症)、糖尿病、痛風などの生活習慣病やメタボリックシンドロームの診断、生活習慣の改善指導、および治療管理を行います。
- 健康診断や人間ドックなどで異常所見がみられた場合、異常所見の解説、再検査、適切なアドバイスを行います。
- 寝つきが悪い、気分の落ち込み、集中力の低下などもご相談ください。
- ご家族の認知症問題や介護保険の申請などについてもご相談ください。
- 気管支喘息、COPDなどの慢性呼吸器疾患の診療、呼吸器疾患における在宅酸素療法の導入、身体障害者(呼吸器疾患)認定に関してのご相談をお受けいたします。
- 精密検査、専門医の診療や入院が必要であると判断した場合は、速やかに地域連携病院をご紹介いたします。
高血圧症
何らかの原因で血圧が基準値より高くなった状態(最高血圧140mmHg以上、または最低血圧が90mmHg以上)をいいます。ほとんどの場合自覚症状はありませんが、頭痛や肩凝り、めまいなどがおこることもあります。高血圧が続くと、全身の血管で動脈硬化が進み、突然、脳卒中や心臓発作を起こすこともあるため、「サイレントキラー」と呼ばれるほどです。
原因
高血圧の9割は原因が明らかでない本態性高血圧です。
治療
生活習慣の修正を基本に、リスクの度合いによって薬物療法が加わります。
食事や嗜好品を中心に生活習慣を整えることは重要です。
↓
※食塩と血圧
食塩と血圧は関係があるという結果が出ています。
減塩には動脈の柔軟性を高める、腎機能を守る、降圧薬の効果を高めるなどの利点が報告されています。
脂質異常症(高脂血症)
血液中の中性脂肪(トリグリセライド)やLDLコレステロール(悪玉コレステロール)が基準値より高い、またはHDLコレステロール(善玉コレステロール)が基準値より低い状態のことをいいます。
原因
さまざまな遺伝的要素や体質、食習慣、運動不足、肥満などが背景にあることが多いようです。
放っておくと
とくにLDLコレステロール値が高いと、動脈硬化が進み、脳梗塞、心筋梗塞など血管系の病気が起きやすくなり、中性脂肪値が高いと急性膵炎を起こすこともあります。
治療
動脈硬化を進めないようにすることが重要です。食事や運動を含んだライフスタイルの改善を行い、動脈硬化による病気を起こすリスクが高いときには薬物療法が追加されます。
糖尿病
現在、日本人の40歳以上の3人に1人以上が糖尿病(糖尿病予備軍)と推測されています。初期の段階ではほとんど無症状のため、血液検査をして初めて糖尿病と診断されることが多いです。
原因
膵臓から分泌される血糖を下げる働きを持つ「インスリン」というホルモンの不足や、その作用不足で血液中の糖の濃度が高くなった状態(高血糖)が続く病気です。
放っておくと
糖尿病の進行により、3つの大きな合併症(網膜症・腎症・神経障害)が知られており、網膜症による失明や、腎不全、心筋梗塞や脳卒中など、生活の質(QOL)を低下させる病気にまで進展することがあるので注意が必要です。
治療
糖尿病初期の段階では、食事療法と運動療法が主になります。初期の段階であれば、血糖が改善することも少なくありません。しかし、進行すると薬物療法が必要となります。血糖値を改善させて合併症を防ぎ、健康な人と変わらない活動的な毎日を続けられるように治療を継続しましょう。
痛風・高尿酸血症
血液中に尿酸が多くなった状態をいいます。尿酸塩(尿酸の結晶)が関節などにたまると激しい痛みを伴う炎症発作(「痛風」発作)を起こすことがあります。痛風は9割以上が成人男性に発症しますが、痛風の背景には持続する高尿酸血症があることから、高尿酸血漿の定義は血清尿酸値>7.0mg/dL(年齢・性別を問わず)と定められています。
原因
血液中に尿酸が増える原因は、①尿酸が体内で多く産生される、②尿酸の排泄が悪い、③ ①と②の両方、が考えられています。
放っておくと
尿酸値が高い人は、痛風だけでなく様々な病気を合併すると考えられます。(脳血管障害、心疾患、腎障害(痛風腎)、尿路結石、痛風結節)
治療
治療は、薬物でのコントロールが中心となりますが、生活習慣の修正も大切です。
花粉症
スギやヒノキなどの植物の花粉が原因となり、アレルギー症状をおこす病気です。 季節性アレルギー性鼻炎ともいわれます。
症状
鼻の症状(くしゃみ・鼻水・鼻づまり)だけでなく、眼の症状(かゆみ、なみだ、充血等)を伴う場合が多く、その他には咳、のど・皮膚のかゆみ、頭重感、倦怠感、不眠、からだや顔のほてり、イライラ感など、からだの各部位で多くの症状がおこります。 そのため、肉体的にも精神的にも意欲が低下して、QOL(日常生活の質)が大きく損なわれてしまうことがあります。
治療
花粉飛散情報を参考に、風の強い日は外出を避ける。外出の際にはマスクや帽子、メガネ(ゴーグル)などの花粉対策グッズを使用しての花粉回避が重要です。
また帰宅時は衣類を払って、花粉を直接家の中に持ち込まないようにし、手洗い・うがいだけではなく眼や顔も洗いましょう。花粉が飛ぶ前から予防的に薬を服用すると症状を抑える高い効果が期待できます。
一方で、症状が進んでしまうと喘息症状まで出ることがあります。
花粉症は、予防と早めの治療が大切です。
診断には、血液検査などで簡単に検査ができます。自己判断をせずに早めに受診されることをお勧めします。
気管支喘息
喘息は、空気の通り道である気道(気管支など)に炎症が起き、空気の流れ(気流)が制限される病気です。気道はいろいろな吸入刺激に過敏に反応して、発作性の咳や喘鳴(細くなった気管支を空気が通る時に生じるゼーゼー、ヒューヒューいう音)、呼吸困難が反復して起こります。症状は夜間や早朝に起こることが多く、軽いものから生命に関わるほど重症になる場合もあります。ハウスダスト・ダニなどのアレルゲンや呼吸器感染症、大気汚染、喫煙、気候の変化などが増悪因子となります。
適正な治療が行なわれないと炎症とその修復が繰り返される過程で気道の壁が厚くなって、空気の流れ(気流)が元に戻らなくなり、気道の敏感さ(過敏性)も増します。このようになる前に治療が必要です。
咳喘息
慢性咳嗽(がいそう)の原因の中で、最も頻度が多いと考えられています。
気管支喘息とは異なり、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)を伴いません。
咳は喘息と同じく、夜間や早朝に強く、冷気・暖気・タバコの煙・会話・運動・飲酒・緊張などが誘因となります。
約30%の患者さんが気管支喘息になると考えられており、適切な治療が推奨されます。
COPD(慢性閉塞性肺疾患)
慢性閉塞性肺疾患(COPD:Chronic Obstructive Pulmonary Disease) とは以前、「慢性気管支炎」(頑固な咳やたんが続き気管支が狭くなる疾患)と「肺気腫」(肺の組織が破壊されて息切れや呼吸困難を起こす疾患)と呼ばれていた疾患の総称です。初期には自覚症状がほとんどない場合が多く、ゆっくりと進行して、しだいに重症になっていきます。
症状としては坂道や階段を昇る時など、身体を動かした時に息切れを感じる「労作性呼吸困難」が特徴です。慢性の咳や痰もみられます。初期には「年のせい」と考えてしまうことも多く、かなり進行してから、気づく場合が多いのが大きな問題です。
日本では40歳以上の8.5%(男性13.1%,女性4.4%)、COPDの潜在患者は530万人以上と推測され、治療を受けているのはそのうち5%未満といわれています。未治療の患者さんが大変に多いのです。別名"タバコ病"ともいわれるように、最大の原因は喫煙で、患者さんの90%以上は喫煙者です。
長年にわたる喫煙が大きく影響するという意味で、まさに"肺の生活習慣病"です。
タバコを吸わない人でも4.7%の人がCOPDにかかっています。これは、副流煙による"受動喫煙"の危険性を示しています。喫煙者が近くにいる人は、タバコを吸わなくても喫煙者と同等か、それ以上の有害物質を吸い込んでいるのです。
家族がヘビースモーカーだったり、分煙されていない職場で仕事している人はCOPDにかかる危険性が高まります。
予防には禁煙が第一ですが、症状がある場合には、吸入治療などを行います。
インフルエンザ
インフルエンザウイルスの感染により起こります。典型的な症状は、突然の高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛などで、のどの痛み、咳、鼻水なども見られます。普通の風邪に比べて全身症状が強いのが特徴です。
感染発症すると、高熱が出て体調が悪くなることにくわえて、1週間前後の休養が必要となります。流行する前に、インフルエンザワクチンを接種して予防することをお勧めします。
毎年の流行期間が、12月~3月ですので、11月中に接種されますと効果的です。感染した場合は速やかに治療することが重要です。
かぜ症候群
鼻からのどにかけての空気の通り道である上気道に起こる呼吸器の感染症です。くしゃみ・鼻水・鼻づまり・咳・痰・のどの痛み・悪寒・発熱・頭痛・関節の痛み・だるさなどの症状があります。一般的には、数日~1週間ほどで自然と治りますので、安静が重要です。治療は咳には咳止め、痛みには鎮痛剤、熱には解熱剤というように対症療法が中心になります。
安静にすることが一番の治療ですが、のどの痛みが強い場合や激しい咳、痰や鼻水が黄色や緑色で濁っている、などの症状がある場合は早めに医療機関を受診しましょう。
小児科

急な発熱、鼻水、せき、のどの痛みなどのかぜの症状や腹痛、下痢、便秘、嘔吐、発疹、湿疹など、一般にお子さまによく見られる症状について診療を行います。
診療の結果、精密検査や入院が必要と判断した場合は地域連携病院へご紹介しております。
発熱
乳幼児はしばしば熱を出しますが、その原因のほとんどはウィルスや細菌などの病原微生物の感染です。 保育園や幼稚園に入園した初年は特に頻回に熱を出すことが多いものです。 体温が37.5℃以上は発熱と考え、こまめに体温を測り、記録し、熱の経過を追うことが大切です。 発熱以外の症状、例えば顔色が悪い、嘔吐が続く、水分が取れない、活気がなくぐったりしている等の症状を伴っているようであれば早めの受診をお勧めします。
咳
咳の原因はいろいろあるのですが、やはり病原微生物による気道の感染が最も多いと考えます。長期間(目安として3週間以上)咳が続いている場合はマイコプラスマや百日咳の可能性もあります。長い期間(目安として3週間以上)咳が続き、気温の寒暖差や台風(強力な低気圧)の接近で咳がひどくなる場合は、気管支のアレルギー(ハウスダスト、ダニなど)が原因となっている可能性があり、気管支喘息に移行することもあります。咳はどのくらい続いている?(2~3日、1週間、1か月)、咳の出る時間帯は?(深夜、明け方、起床時、昼間、1日中)、痰はからんでいる?咳込んで眠れない?呼吸が苦しそう?などの症状が重要なポイントです。
鼻水
鼻水には透明でサラサラした水様性鼻汁と黄色ないし緑色でドロッとした膿性鼻汁の2種類があります。
花粉症(アレルギー性鼻炎)や風邪の初期では前者が、副鼻腔炎(蓄膿症)や風邪の後期では後者が多いようです。
膿性鼻汁の中には風邪の原因となった病原微生物(ウィルスや細菌)が多量に含まれていることもあるため、積極的に鼻をかむか、耳鼻科受診し吸引を行って微生物ごと体の外へ出しきってしまうことが大切です。乳幼児では膿性鼻汁が長引いているうちに中耳炎になってしまっていることがあります。
腹痛
腹痛の原因としては風邪、感染性胃腸炎、便秘、ぜん動痛(腸管の収縮に伴う痛み)などがあります。痛みが急で激しい場合は緊急を要する病気も考えなくてはなりません。 痛み以外の症状、たとえば、嘔吐、下痢、発熱、顔色などにも注意して観察する必要があります。
呼吸苦
呼吸が苦しそうな時は、喘息発作、喉頭炎(クループ)、肺炎、気道異物、アナフィラキシー(食物アレルギー)による呼吸器症状などを考えなくてはなりません。 顔色が悪く、表情が弱々しい時は早急に医療機関の受診が必要です。
訪問診療 現在対象を限定させていただいております
通院が困難な患者様の居宅(自宅や入居施設)に、定期的に診療にお伺いし計画的に健康管理を行うものです。
地域の病院や介護事業者の方々と連携・協力しながら、患者様が在宅で安心して療養生活を続けられるよう総合的にサポートします。
現在、訪問診療対象者は、全ての訪問診療希望者ではなく、当院に長年定期的に通院していた患者様限定で総合判断より実施しています。
【訪問診療を受けるまでの流れ】
訪問診療のご相談・お申し込み
↓
訪問診療計画の作成
↓
医師による訪問診療開始
(月2回程度)
【訪問診療における制度】
訪問診療は基本的に保険適応で行うことができます。
<国民健康保険・社会保険>
一般の医療保険の一部負担金と同じ扱いになります。
<後期高齢者医療保険>
医療費の1割(または3割)が一部負担金となります。
<障がい者・生活保護>
各市町村の減免と同じ扱いになります。
【実際の訪問診療における費用について】 診療報酬改定により変更あり
~1割負担の方を月2回、訪問診療をする場合~ 例
1660円 + 4150円 + 588円 = 6398円 となります。
在宅患者訪問診療料(医療保険) 例
自宅で療養しているが、環境や病気、けがの為に病院へ通って治療を受けることが難しい方に対して、医師が定期的に訪問して診療を行うこと(通院できる方は対象外です)
→1回あたり830円/1時間以内
※診療が1時間を超えた時、30分ごとに100円増しになります。
在宅時医学総合管理料(医療保険) 例
自宅療養中の方に対し、個別にご自宅での療養計画を作成し、医師が定期的に訪問
して診療を行い、総合的に医学管理を行うこと。
→月2回以上訪問診療を行った場合、1ヶ月あたり3850円
月1回のみ訪問診療を行った場合、1ヶ月あたり2450円
※処方箋を交付しない場合、300円の加算があります。
居宅療養管理指導費(介護保険) 例
環境や病気、けがの為に通院することが難しい方を対象に、医師や看護師などが自宅を訪問し、健康管理や指導を行うこと(要介護1~5までの方が対象)
介護保険証をお持ちの方のみ対象です。
→1回あたり294円/月2回まで(介護保険1割負担の場合)
※検査・処置・注射等に係る費用、お薬代(調剤薬局の費用)、遠方時の交通費、緊急時の往診料等は別途必要となります。
※3割負担の方はそれぞれ3倍となります。
※要支援1~2の方は、介護予防居宅療養管理指導が適応となります。
介護
当院は、指定居宅療養管理指導事業所です。
通院が困難な患者様の居宅を訪問して患者様の病状や心身の状況、生活環境などを把握し、指定居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)が居宅サービス計画の作成に必要な情報を提供するとともに、患者様及びご家族の方に療養上の管理・指導・助言などを行います。
当院で行なっている感染症迅速検査
インフルエンザ(A型、B型)
鼻から綿棒で検体を採取し判定。全年齢で保険適用あり。
溶連菌感染症
咽頭から綿棒で検体を採取し判定。全年齢で適用あり。
アデノウイルス感染症
咽頭、結膜から綿棒で検体を採取し判定。全年齢で保険適用あり。

RSウイルス感染症
鼻から綿棒で検体を採取し判定。
保険適用は以下の場合
- 1歳未満の子ども
- 入院中、あるいは入院が必要と判断された患者
- 1歳以上で、自費扱いの場合は3,000円
マイコプラズマ
咽頭から綿棒で検体を採取し判定。全年齢で保険適用あり。
ノロウイルス感染症
便を用いて判定。3歳未満 及び 65歳以上が保険適用。
- 自費扱いの場合、3,500円
新型コロナウイルス感染症抗原検査
鼻咽頭ぬぐい液を用いて診断します。約10分間で結果が判明します。
初診の方へ
はじめに受付に健康保険証、各種医療証、医療券をご提示ください。
お薬手帳をお持ちの方はご持参ください。
問診票をご記入いただきます。
︎麻しん、風しん、おたふく、水ぼうそうなどの感染症の疑いがある方は、はじめに受付にお申し出ください。
※問診票はダウンロードして、事前にご記入してお持ちいただけます。